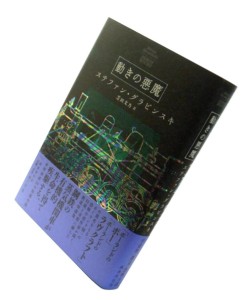2021年4月13日
ジョン・スタインベック(1902-1968)の晩年の作「チャーリーとの旅」(Travels With Charley: In Search of America, 1962)はスタインベックが1960年に愛犬チャーリーと特注のキャンピングカーで3カ月にわたってアメリカを周遊したノンフィクション紀行文で、ノーベル文学賞を受けた年に出版され、ベストセラーになりました。今でも多くの読者がいると思います。初めて読んだのは翻訳本で、1987年にサイマル出版会が出した大前正臣訳(改訂版)でした。

大前正臣訳の「チャーリーとの旅」の初出は1964年(弘文堂)ですから、オリジナルが出版されてから2年後に翻訳が出ています。また、2007年には別の訳者の本(竹内 真訳 ポプラ社)も出版されています。
アメリカの路上文学は好きで、いろいろと読みましたが、この本が特に楽しかったのは、スタインベックと同行した老犬チャーリーがスタンダードプードルだったことです。学生時代に読んだコンラート・ローレンツの「人 イヌにあう」でプードルを知って、「チャーリーとの旅」を読んで、スタンダードプードルを飼うことになりました。昨年亡くなったパスカルJrは我が家で2頭目のスタンダードプードルでした。
さて、サイマル出版会の「チャーリーとの旅」の裏カバーには次のように書かれています。
「ノーベル賞作家スタインベックは、アメリカ再発見を志し、愛犬チャーリーを連れて、自らキャンピングカーを運転するアメリカ一周の旅に出た。この作品は、その時の孤独と模索の旅行記で、文豪一流のユーモラスな筆致で迫る”変わらざるアメリカ”の姿は、凡百のガイドブックにまさる、アメリカの本質への案内でもある。」
また、シカゴ・トリビューン、ボストン・ヘラルド、朝日新聞、毎日新聞などの書評も記載されていて、いずれも旅の記録として見事な筆致という雰囲気で絶賛しています。
私ももちろんノンフィクションとして読みましたし、読後感想として、1983年にアメリカ横断ドライブをする前に読んでいたら、ルートを少し変えていたかもしれないと思ったほどでした。
ところが最近、プードルのことをネットで調べていたら、もちろん「チャーリーとの旅」がヒットするのですが、その中で気になる話題を見つけました。スタインベックはチャーリーと旅をしていなかったという記事です。
最初に読んだのは”Reason”というネット上のフリー・マガジンでした。アメリカのジャーナリストBill Steigerwald氏が2011年春に書いた記事(英語)で、タイトルは「ごめんね、チャーリー(Sorry, Charley!)」となっています。
Steigerwald氏は半世紀前にスタインベックが見聞きしたアメリカ各地での風土・文化を調べるために、自分自身で「チャーリーとの旅」の1万マイルのルートを辿り、日程を確認していったそうです。それで明らかになったのは、スタインベックが描写した場所・場面、人との交流の記述がスタインベックの当時の行動記録とほとんど一致せず、架空の描写であると判断せざるを得なくなったというものでした。
このReasonの記事は、Bill Steigerwald氏自身の著書「Dogging Steinbeck: Discovering America and Exposing the Truth about ‘Travels With Charley’, 2012」(未読)の抄録だろうと思われます。
この話題はWeb版のThe New York TimesにCharles McGrath氏の署名記事(2011年4月)で紹介されています。こちらの記事のほうがカラー写真も入っていて、よりわかりやすく書かれていました。
McGrath氏の記事では、ジョン・スタインベックの息子に確認したところ、父は購入したキャンピングカーでの旅行などしておらず、自宅に置いたキャンピングカーの中で原稿を書いていただけと証言しています。
もう10年も前の記事ですから、これが事実だったら日本でもそれなりの議論と解説が出ているだろうと思って、日本語でネット検索をしてみましたが、何も見つかりませんでした。
友人のアメリカ文学の専門家に聞いてみました。彼はスタインベック研究者ではなく、また「チャーリーとの旅」も未読だったそうですが、日本のスタインベック学会で「チャーリーとの旅」についてのフィクション疑惑の話題は聞いたことがないということでした。でも、フィクションのほうがスタインベックのアメリカ像を表現しているのでは、というご意見でした。
Wikipedia(英語版)にも「チャーリーとの旅」の話題が取り上げられていました。当時のスタインベックは体調も優れず、チャーリーだけを乗せて3カ月のキャンピングカーでの旅行は無理だったようです。未見ですが、原書2012年版にはそういう解説が載っていると書かれています。
ともかく、久しぶりに「チャーリーとの旅」を読み直してみました。上記の情報から私の読書態度が変化しているのは否めませんが、確かに実際の旅をしている時系列での描写という流れはあまり感じられなかった一方、取り上げられているエピソードは具体的で読み応えがありました。最後のテキサスやニューオリンズあたりの話題は、21世紀の読者にとってはステレオタイプ的要素が濃いように思えますが、それは60年を経た昨今でもアメリカ文化の根にあるように感じます。
晩年には作家として行き詰まっていたという批評もあるようで、少し様態を変えた叙述を試みたのかもしれません。その点では、こういうノンフィクションらしいフィクションを書き上げたのがスタインベックだったのだろうと今は感じています。個々の文化論トピックは時系列とは無関係のノンフィクションで、紀行文としての記述の様態がフィクションだったと言えそうです。
フィクションを実話の紀行文であると明記したことが問題なのでしょうね。これはフィクションですと明記すれば、ほとんど実話でもかまわないようですが、逆は許されないのかもしれません。Steigerwald氏がfraud(詐欺)という言葉を使っているのはそのことを示しているようです。
でも、「チャーリーとの旅」での地元民との会話は存在しなかったとしても、スタインベックがいつかどこかで地元民と会話して、それらを整理したものであれば、それはノンフィクションと言ってもいいように思えます。「怒りの葡萄」はフィクションですが、その時代のアメリカを切り取った文化論としてはノンフィクションと言える、というのと同じ構造なのかとも思います。小説にフィクション・ノンフィクションの厳密な区別をつける必要はなさそうです。
スタインベックの「チャーリーとの旅」がフィクションだとわかってから読み直してみても、私の愛読書の位置づけの変化はありませんでした。スタインベックの創作としてそれだけの内容を持っているとあらためて感じました。スタインベック自身がフィクションだと書いておいてもかまわなかったと思いますが、60年前の話ですから、どちらでもいいような気もします。
旅行に連れて行けなくてゴメンネ、となったチャーリーはドライブ好きで利発なスタンダードプードルだったようです。私が「チャーリーとの旅」を読んで選んだ最初のスタンダードプードルのショパン、その後のパスカルJr、どちらもドライブが大好きでした。長距離ドライブはしていませんが、一緒に過ごした長い時間を思い出します。