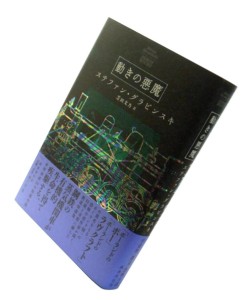いろいろな連想が広がっていく、とても興味深い本を見つけました。
ステファン・グラビンスキの「動きの悪魔」(芝田文乃訳 国書刊行会 2015)です。
ポーランドのポー(エドガー・アラン・ポー)と呼ばれる100年前の作家、グラビンスキ(Stefan Grabiński, 1987-1936)の初の邦訳だそうです。1919年に出版された短編集に、後の短編をいくつか加えた構成になっています。すべて鉄道に絡んだ話ですが、「鉄道・旅行ファン」が広く好むものではないかもしれません。ポーと比較されるように、初期の怪奇小説とかホラーとかに分類されています。私としてはあまりポーと共通点があるようには感じませんでしたが、読者の心を動かす独特の雰囲気を持っています。
出版された時期はちょうど第一次世界大戦が終わり、ポーランドは独立しています。1936年にポーランドは再びドイツに占領されますが、それまではピウスツキ体勢で、しばらくは喜びが多かったのでしょうか。そのような頃合いに出版された本書はそれなりに売れたそうです。
グラビンスキの経歴は中学教師で、鉄道に関する仕事はしていません。しかし、明らかに旅行好きで鉄道好きだろうと思います。それは機関車の構造から信号のシステムまで、よくわかった描き方をしていることから推察できます。
イ ギリスで蒸気機関車が走り出して100年余りで、ヨーロッパ大陸にも鉄道網が張り巡らされました。鉄道は各国の威信をかけた巨大事業であり、すべての鉄道会社は鉄道・車両の維持・管理に官僚的な制度を作り上げていたようです。オリエント急行が走り出したのは1883年ですから、大型の長距離用高速蒸気機関車が作られるようになり、客車内は快適になってきて、国際旅行もゆったりと過ごせるようになりました。
当時にポーラン ドで走っていた機関車はよくわかりません(ソヴィエト製かも)が、ドイツでは王立バイエルン鉄道の名車S3/6(1908~ 当模型鉄道所属の写真)など、高性能の機関車が走っていました。
かつてない輸送能力を持つ巨大な機械が爆走する鉄道を眺めた一般市民は驚異・畏敬・恐怖・憧れを感じていたのではないでしょうか。でも、巨大さは今も変わらないものの、当時の鉄道システムは、まだすべての装置を人手で制御していました。機関士が機関車を操作するのは当然ですが、すべての安全確認も人の作業です。電気仕掛けの信号は一般的でなく、腕木式信号機、分岐器(ターンアウト・スイッチ)などを手動で動かしていました。電気を使うのは照明と駅間の有線電信くらいだったでしょう。
規則で厳密に決められた手仕事に熟練した鉄道員は誰もが自分の仕事にプライドを持っていたと思いますが、誰か一人でも、与えられた仕事の規則を逸脱してしまうと、それは大惨事に直結します。そして、異常な逸脱に合理的な理由があるとは限らず、そのような逸脱が現実のものとならない保証はありません。
この本に収録されている作品のいくつかは怪奇・怪異な現象を物語っていますし、本のタイトルとなっている「動きの悪魔」は、残忍さではポーを連想させるものの、ポーの多くの作品のように納得させる説明はありません。読み進むにつれて、怪奇・怪異と言うよりは、鉄道員の鉄道への強すぎる愛情がもたらした逸脱を描いた作品が多いような気がします。「音無しの空間」、「機関士グロット」など、怪奇的な印象というよりも、愛情の強さに切なくなるところがあります。
怪奇的と思えたのは「信号」でした。この作品は映画「渚にて」(1959)を思い出させてくれました。「渚にて」は1950年代の米ソ核戦争についての悲劇的シナリオで、怪奇小説(映画)ではありませんが、心の緊張感と切なさは強烈でした。米ソの核戦争が起こり、すでに北半球では人がいなくなった地球で唯一生き残ったアメリカの原子力潜水艦が、無線機に入り続ける、解読できないモールス信号を発する場所を探しに行きます。まだ生きている人がいることを期待したのです。しかし、たどり着いた現場で乗員が見たのは、人ではなく、風にそよぐカーテンに紐で結びつけられたコーラの空き瓶がランダムに押す電鍵でした。
電鍵というのは、手で押してモールス信号を発生させるスイッチです。手持ちの電鍵の写真を入れておきます。手前左が旧日本海軍の電鍵、手前右がアメリカの典型的な電鍵です。いずれも押す時間で短点(トン)と長点(ツー)の長さを調節してモールス信号を作ります。後ろは私が80~90年代に愛用していた、親指と人差し指で側面から押す方式で、電子回路が必要ですが、左側を押すと単点、右側を押すと長点が連続的に出て、とても早く打てて楽ちんです。
さて、「信号」では、信号の発信源は電鍵で信号を送りながら亡くなって久しい信号手の指の骨です。しかし、それが怪奇的というわけではありません。「信号」が怪奇的だと思うのは、送られていた信号が解読不能ではなく、事故発生の緊急信号だったという点です。そして、半ば白骨化した信号手の死体を運び出した後に、その信号が意味した大事故が起こることになります。読んでいて、このあたりの展開を受け入れる気持ちになるかどうかが、グラビンスキ、さらには怪奇小説を評価するポイントになるような気がします。
翻訳は100年前の世界をイメージしやすく、読みやすいと思いました。一つだけ、「待避線」という作品タイトルの訳語については、訳者も後書きで説明してはいますが、原題は「引き込み線」のようです。「待避線」というタイトルで読み進んでいくと違和感を感じました。訳者は語感を重視したようですが、引き込み線と待避線を区別する人にとってはマイナスだったかもしれません。